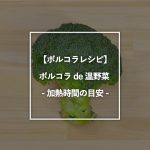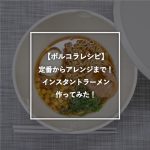味噌容器メーカー直伝!手作り味噌を作ろう – 最適な容器でもっと美味しく –
こんにちは。
だんだん寒くなってきましたね。
寒い時期に仕込む”手作り味噌”の季節がやってきました。

「お家で手作り味噌を作ってみたいけどどうやって作るんだろう…」
「せっかく作るなら美味しい味噌を作りたい!」
そんな方必見!味噌作り初心者でも大丈夫。
本記事では作り方からおすすめの味噌容器までご紹介しています。
ぜひ最後までご覧になってくださいね。
手作り味噌の基本
1. 清潔さ

味噌作りには発酵が伴うため、雑菌の混入を防ぐことが大切です。
道具(ボウル、すり鉢、容器など)はよく洗い、使用前に煮沸消毒やアルコール消毒を行うと安心です。
手も十分に洗浄してから始めましょう。
2. 温度管理
発酵には温度が大切です。
味噌は1年を通して発酵しますが、25℃以上になると発酵が進みすぎることがあります。
1月〜2月の冬場に仕込み、涼しい場所で熟成させるのが理想的です。
3. 空気と密封
容器に仕込む際、空気に触れすぎるとカビが発生しやすくなります。
できるだけ空気に触れないようにしましょう。
リスのおすすめ味噌容器は完全密封。カビ対策はもちろん、ニオイ漏れも防いでくれますよ。
4. 熟成期間を守る
家庭の環境によって発酵の進み具合が異なりますが、最低でも6ヶ月〜1年は待つことが必要です。
熟成が進むほど旨味が増すので、気長に待ちましょう。
早速味噌を作ってみましょう
リスのおすすめ味噌容器を使えば、下記の量を簡単に作ることができます。
みそ容器 6型

手順
1. 大豆の準備

1-1. 浸水:大豆は一晩(10〜15時間)水に浸けておきます。大豆は水を吸って2〜3倍に膨らみます。
1-2. 茹でる:水を切った大豆を新しい水に入れ、柔らかくなるまで約3〜4時間ほど茹でます。
目安としては大豆が指で簡単につぶれるぐらいの柔らかさが理想です。
2. 麹と塩の準備

1-1.米麹または麦麹と塩を混ぜ合わせた、塩きり麹を作ります。
これをしっかりと混ぜておくことで、発酵が均一に進みやすくなります。
3. 大豆をつぶす

1-1. 茹でた大豆が冷めないうちに、すり鉢やフードプロセッサーでつぶします。
手でつぶす場合は潰しやすい温かさまで冷まします。ペースト状にするのが理想ですが、少し粒が残っても構いません。
4. 大豆と塩きり麹を混ぜる

1-1. 3でつぶした大豆と2で作った塩きり麹をよく混ぜ合わせます。
水分が足りない場合は、茹で汁を少しずつ足して混ぜやすい硬さに調整します。
1-2. 混ざったら、団子状の味噌玉(こぶし大)を作り、空気を抜きながら成形しましょう。
5. 容器に詰める

1-1. 消毒した保存容器に味噌玉を隙間なく詰めていきます。
1-2. 詰め終わったら、表面を平らにならし、塩を少量振っておくか、ラップで覆います。

6. 発酵・熟成
1-1. 容器を風通しの良い涼しい場所に置きます。発酵には半年から1年ほどかかります。
1-2. 夏場を越えると発酵が進み、秋ごろには食べられる状態に近づきます。途中、表面にカビが発生する場合は、カビの部分だけをそっと取り除いてください。
1-3. 表面に汁(たまり)が浮いてきたら時々かき混ぜましょう。
説明書付き!おすすめ味噌容器はこちら
リス株式会社では味噌容器を製造、楽天店にて販売しております。
・安心の日本製
・プラスチックメーカーならではの頑丈な作り
・初心者にも優しい説明書付き
みそ容器 6型(出来上がり量 5kg)

みそ容器 11型(出来上がり量 10kg)

お客様レビューでは★5.0と高評価!(2024.10.30時点)
「頑丈なつくりなので、重たい味噌でも安心して入れられます」「大きさも丁度良かったです」「味噌溜まりもできて 嬉しい」など嬉しいお言葉がたくさん!
ぜひあなたも使ってみて実感いただけたらと思います。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
一見、難しそうな手作り味噌も、リスのみそ容器を使えば安心!
時間をかけてゆっくりと作ることで、風味豊かな味噌を楽しむことができます。
説明書付きの便利な味噌容器、ぜひチェックしてみてくださいね。